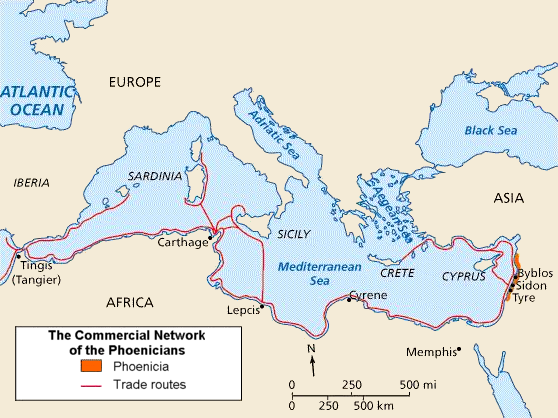ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』ですが、たまに、以下のような発言があります。
@05tolahi2 ゲーテという人が、ヨーロッパが生んだ最大の発明の1つは複式簿記であると言いました。それくらいすごいらしいね。僕は簿記は分からないんだけど・・・簿記は学んでおくといいと言われますね。— 駄犬 (@daken_ver0_03) 2015, 9月 1
余談やけど日本政府は単年度であり複式簿記を使ってないんよ。
ところが最近、TL上でこのような御発言を見かけました。
ゲーテのこの一節を得意げに引く会計方面の方々は『ヴィルヘルムマイスターの修行時代』を読んでいないか、読解力にかなり難ありと言えましょう。https://t.co/uWD2zRH08ahttps://t.co/o1zqYM3WOw https://t.co/9LT5u24n9d— 河村耕平 (@khkawamura) 2016, 2月 8
@yukaohno_econ @tknr_adch 『修行時代』にヴィルヘルムの友人が「複式簿記は人類最高の発明の一つ」と言うくだりがあるんです。いくつかの会計学の本では「ゲーテは複式簿記は人類最高の発明の一つ」と述べた、と書かれているんですが、それは恥ずかしい間違いで、(続)— 河村耕平 (@khkawamura) 2011, 9月 23
@yukaohno_econ @tknr_adch 小説のなかで、演劇に燃える主人公ヴィルヘルムと対比して、商売ことしか頭に無いその友人をなかば揶揄するように、「人類最高の発明の一つ」と言わせてるんです。なのでゲーテの言葉と取るのは間違い、という実にどうでもよい話でした…。(了)— 河村耕平 (@khkawamura) 2011, 9月 23
そういえば、私(監査たん)も未読だと気付き、帰りに本屋に寄って購入いたしました。本日は、そのまとめです。
 |
| 若い頃のゲーテ |
▶︎場面
「複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも、経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ 。」の発言が登場するのは、第1巻の10章(上巻)です。この本が、全巻から構成されることを考えると、かなり最初の方です。主人公ヴィルヘルムは、恋人マリアーネと暮らすことを夢見ています。彼は、役者業を得るため、父親を半分騙して、商用の旅に出ます。登場する場面は、彼の演劇を手伝う友人ヴェルナーと荷造りを行っている時です。
▶︎ヴェルナーの発言とヴィルヘルムの反論
ヴィルヘルムが、昔の台本などを見てもたもたしているのを見て、ヴェルナーが声をかけます。
友人ヴェルナー:「そんなものは捨ててしまえよ。火にでも焚べるんだな。その着想なんて愚の骨頂だね。構成にしたって、もうあの頃から僕は嫌でたまらなかった。お父さんだって怒ってたじゃないか。詩の出来はいいかもしれないが、考え方がまるで間違っている。商売を擬人化した婆さん、しわくちゃの惨めったらしい占い女をまだ覚えいるよ。あの人物は、どこか薄汚い小商いの店から仕込んできたんだろう。あの頃君は、商売ってものがまるでわかっていなかったんだ。」
主人公のヴィルヘルムは、お父さんがしている商売に疑問を抱き、自分の演劇のネタにしていたのです。この演劇については別の記事に書く予定です。そして友人ヴェルナーは続けて以下のよう述べています。
友人ヴェルナー「真の商人の精神ほど広い精神、広くなくてはならない精神を、僕は他に知らないね。商売をやってゆくのに、広い視野を与えてくれるのは複式簿記による整理だ。整理されていればいるでも全体が見渡される。細しいことでまごまごする必要がなくなる。複式簿記が商人に与えてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が生んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも、経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ。」
この友人ヴェルナーの複式簿記最高発言は、現代でも色々なところで引用されています。
複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも、経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ 。— 【公式】日本商工会議所検定 (@jcci_kentei) 2015, 4月 15
(ゲーテ:ヴィルヘルム・マイスターの修行時代 より
これに対して、主人公ヴィルヘルムは以下のように反論します。
主人公ヴィルヘルム「君は、形式こそが要点だと言わんばかりに形式から話を始める。しかし君たちは、足し算だの、収支決算だのに目を奪われて、肝心要の人生の総決算をどうやら忘れているようだね」
▶︎誤解
ゲーテが複式簿記を「人間の精神が生んだ最高の発明の一つ」とは言ってないですね(笑)しかし、友人ヴェルナーの発言から当時、商人にとって複式簿記は高い評価を得ていたことがわかりました。
注;ゲーテが複式簿記を「人間の精神が生んだ最高の発明の一つ」と評価していたかはともかくとして、過去の会計文献にこれを引用してたのなら、勘違いしても仕方ないですよね。
 |
| ヴィルヘルム・マイスターの修業時代 |
最後までお読みいただきありがとうございました。



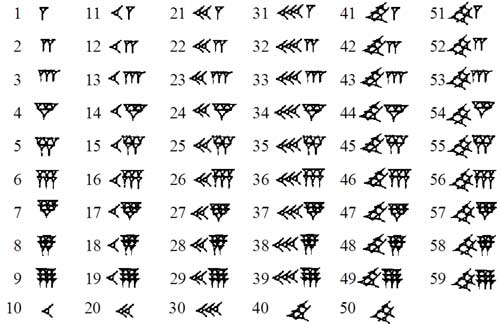


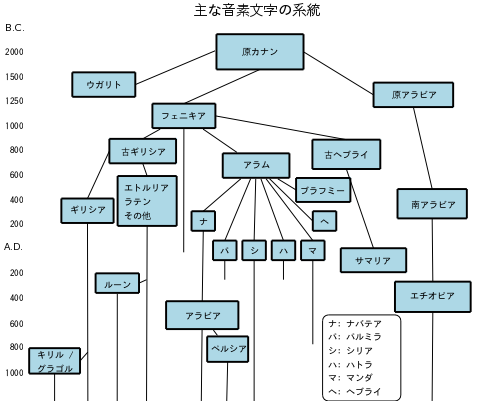
_-_n._23185_-_Socrate_(Collezione_Farnese)_-_Museo_Nazionale_di_Napoli.jpg)